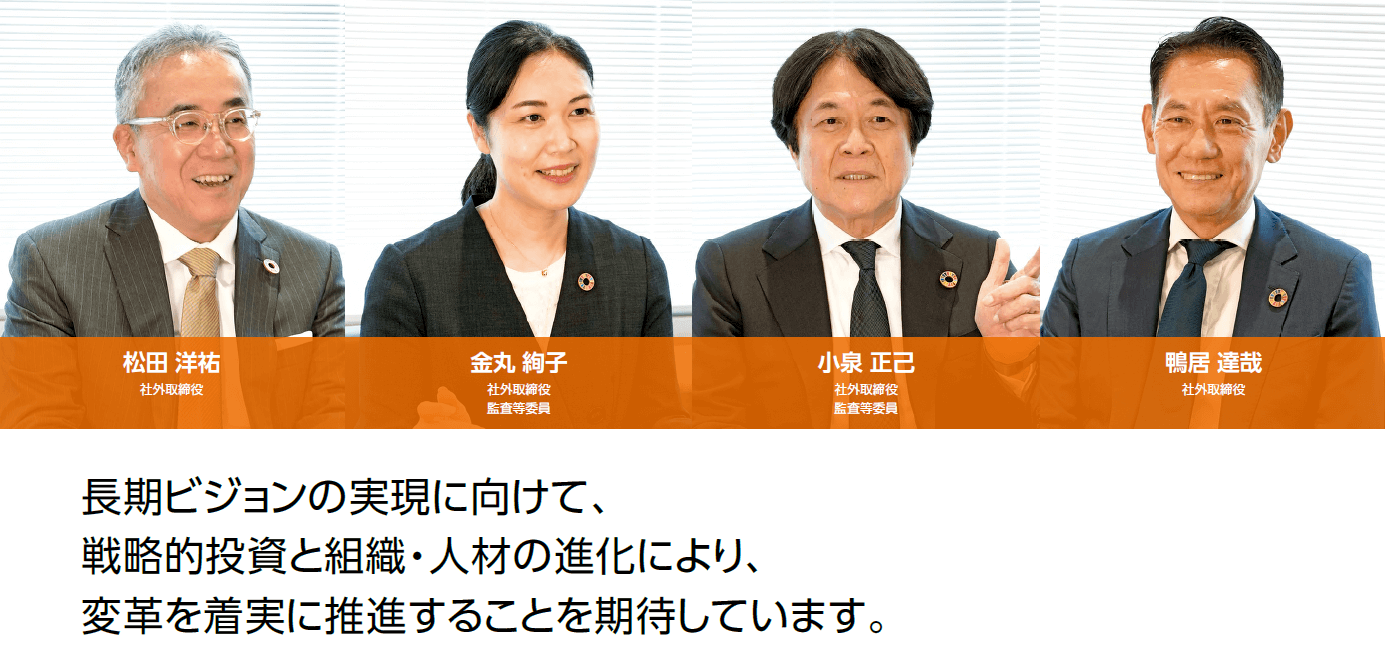
松田 2024年度は、当社が掲げる新たなビジネスモデルへの転換に向けた重要な初年度であり、戦略的なM&Aを積極的に実施した点を高く評価しています。これは単なる事業拡大ではなく、長期視点での戦略的投資でもあり、経営陣も強い覚悟を持って意思決定を行っています。引き続き、アクセルとブレーキのバランスを取りながら拡大路線を推進するとともに、各施策が着実に成果へつながるように運営することが重要です。特に、成長のスピードを維持するためにも、不採算事業については徹底的に見直し、ROEの持続的な改善を図る必要があります。
小泉 私が当社の社外取締役に就任したのは2021年ですが、当時は5カ年ローリングプランのもと、クルマを利用するシーンに合わせたサービスを提供するために6つのネットワークの構築と5つの事業基盤の強化を進めました。これらの取り組みを経て、2024年度にはM&Aの初期コストや人件費の上昇といったコストを吸収しつつ、増収増益を達成し、計画を上回る成果を上げました。特に、「タッチポイントの創出」「商品・ソリューションの開発と供給」「新たな事業ドメインの設定」という3つの重要戦略が着実に進捗している点は、今後の成長に向けた確かな布石と言えます。拠点が拡大したことによって、今後、顧客数が増加することが見込まれ、中長期的な成長に寄与していくものと期待しています。資本効率についてもROIC・ROEともに改善していますが、PBRが1倍を下回っていることは引き続き課題として認識しています。
金丸 2024年度は、将来に向けたさまざまな仕込みを行いながら目標を達成し、良いスタートを切ることができました。社員のモチベーションも高まっており、組織全体に前向きな空気が醸成されていると感じています。今後、多くの種がどのように花を咲かせていくのか、進捗を注視していきたいと考えています。
取締役会では中期経営計画の進捗報告が定期的に行われており、社外取締役も率直な意見を述べる機会があります。経営陣は、そうした社外取締役からの意見や助言を真摯に受け止めており、今後は、各戦略との関連性を明確にしながら、透明性の高い情報開示を継続していただきたいと考えています。
鴨居 私は2025年6月に当社の社外取締役に就任しました。社外取締役就任のお話をいただいた際には、他の社外取締役と面談させていただき、どのような考えを持って経営に参画しているのかについてブリーフィングを受けました。そして、オンボーディングプロセスにおいては、経営企画部から2024中期経営計画の詳細について当社の戦略と課題を深く理解する機会を得ました。
国内マーケットは、人口減少に伴い自動車販売台数が減少していくことが予想され、お客様との接点のデジタル化や自動車のソフトウェア化など、大きく変化しています。このような事業環境の中、当社は2024中期経営計画で、新たな成長ステージに向けた積極的な投資や、新たな事業ドメインの開拓に注力し、多角化を図ることを掲げています。
計画の推進にあたって、経営陣は、現場を統括するリーダー層とコミュニケーションをしっかり取っており、方針・戦略の浸透を図っていますが、計画をやり切るためには、組織全体の実行力の底上げが不可欠です。具体的には、これまで強固なオートバックス事業を中心として拡大・成長するステージでしたが、特に、新事業を創造していくステージへと進むためには、市場分析力、戦略立案能力、課題解決力といった能力がより一層求められます。また、同じ文化や経験を持つ人だけでの同質的な議論からは、変革は生まれません。当社にない能力・経験を持った人材を外部から積極的に採用し、多様なバックグラウンドを持つ人材の採用・登用を通じ、新たな視点を取り入れていくことが重要です。
そして、サプライチェーンの強化を図ることが必要です。新しい事業を運営するために適切なものとなっているか、サステナブルなものになっているか、デジタルインフラは堅牢で柔軟なものになっているか、といった観点で見直しを進めてほしいと考えています。
小泉 2032年度に売上高5,000億円という目標に向けて新たな事業領域を開拓・拡大していくためには、人材の確保・育成が極めて重要です。当社が物販からサービスへビジネスモデルをシフトする中で、整備士の確保・育成に早期から取り組んできた点を評価しています。
今後、国内市場の縮小が見込まれる中、グローバル展開も重要な成長ドライバーです。これまで海外の事業は苦戦してきましたが、堀井社長のもとで体制を刷新し、縦割りの事業部制から小売と卸売の二軸体制に転換しています。グローバル戦略の再構築に注目しており、今後の展開に期待しています。
また、オートバックス事業が持つ非常に高いブランド力を生かし、革新的な進化を遂げることを期待しています。
松田 業績が伸びていることは喜ばしいことですが、今後の着実な成長に向けては、どの施策が効果を発揮しているのかを的確に分析し、強みをさらに伸ばしていくことが重要です。また、社員が手応えを感じられるよう、丁寧なコミュニケーションを重ねることも欠かせません。2032年度売上高5,000億円という目標は、現状の積み上げだけで達成できる数字ではありません。個別の戦略にとどまらず、非連続の成長を実現するための大きなビジョンと、それを支える強い意志が経営陣に求められます。
小泉 私は当社の社外取締役に就任してから4年となりますが、この間にもお客様のニーズは一層多様化し、車の概念そのものが変化するなど、自動車業界の変革は加速しています。成熟した国内マーケットにおいて、トップラインを伸ばすために、物販や車検サービスに加え、新たなサービスや中古車事業などを通じてお客様とのエンゲージメントを拡大・強化している現在の取り組みは、非常に的確な方向性を示していると感じています。
松田 FC加盟店と当社が共に小売を重視し、オートバックスグループ全体で再成長を目指すという考えのもと、2024年4月にFCパッケージの見直しを実施しました。FC加盟店の離脱のリスクを伴う大きな変革でありながら、果敢に実行した点は非常に意義深い取り組みであると受け止めています。社内でも、「堀井社長だからこそ実現できた変革」と評価されています。
現在、成長に向けた積極的な投資が進められており、投資判断にあたっては採算性を重視しています。これは重要な視点ではありますが、安全な投資を積み重ねるだけでは、規模の拡大にはつながっても、本質的な変革には至りません。新しい事業の立ち上げや変革を推進するためには、必要な機能や人材を有する企業かどうかという観点も含めた、より広い視野での判断が必要です。
金丸 FCパッケージを変更したことは、当社にとって大きな決断でした。現在のところ、変更はスムーズに進み、運営にも支障は見られていません。ただし、今後FC加盟店の業績にどのような変化が生じるか、それが当社の業績にどのように影響するかについては、引き続き注視していく必要があります。
また、サービスの質が維持・向上されているか、顧客満足度の推移についても継続的に確認していくことが重要です。今回の変革が、FC加盟店と当社の双方にとって利益をもたらす「Win-Win」の関係構築につながるものであったかどうか、今後も注視していきたいと考えています。
小泉 当社のパーパス「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」と進化の方向性「出かける楽しさを提案し続ける会社へ」は、長期ビジョン「Beyond AUTOBACS Vision 2032」に関する取締役会での議論において、執行側での検討を踏まえて提示されたものです。取締役会では、パーパスと経営戦略の整合性、当社の強みや競争優位性との関連性、将来のマーケット動向を踏まえ、売上高5,000億円の目標達成に向けた成長ドライバーの具体性、そして投資家に対して説得力あるストーリーを提示できるのかということについて、社外取締役からも多くの意見がありました。
身近なメンテナンス拠点として「総合モビリティアフター業」を目指すにあたっては、現行のパーパスがその方向性を十分に支えているか、必要に応じて新たなパーパスを掲げることも視野に入れるべきだと考えています。
松田 非連続の成長を実現するためには、何を伸ばしていくのかを明確に示す必要があります。そのためにも、オートバックスを変革する覚悟を、インパクトのあるエッジの効いたメッセージとして打ち出すとともに、ビジョンや進むべき方向性を具体的かつ説得力のあるストーリーとして整理し、繰り返し発信していくことが重要です。投資家がそのエクイティストーリーに利益の裏付けを感じられれば、企業価値向上が期待できます。
また、社内では会社の変化に気付かなくても、外部からの評価が高まることで社員の意識やモチベーションが向上し、組織全体に活力が生まれるという側面もあります。経営陣には、こうした好循環を生み出すためにも、より積極的な情報発信をさらに実施してほしいと考えています。
鴨居 私はこれまで複数の企業で社長を務めてまいりました。在任中は外部への情報発信に力を入れており、これは外部の理解を得るためもありますが、社員に対して会社の方向性や価値に気付いてもらいたいという気持ちが強くありました。実際には、外部向けは4割程で、社内向け6割の意識で発信していたと記憶しています。当社の経営陣にも、ぜひそのような視点を持ち、社内外への発信をさらに強化していただきたいと期待しています。
小泉 以前の取締役会では個別の議案審議や業務執行に関わる報告が多かったのですが、現在は、2024中期経営計画のもと、「稼ぐ力」をどのように高めていくのかといった企業価値向上に向けた議論が増え、率直かつ建設的な意見交換が行われています。
今後の検討課題として、取締役の総報酬に占める業績連動報酬(株式報酬)の割合が低い点が挙げられます。長期ビジョンや中期経営計画と連動したインセンティブプランの策定は、経営陣の意識と行動をより戦略的に結びつける上で重要であり、検討を進めるべきテーマだと考えています。
金丸 当社の取締役会の特徴として、社外取締役が経営に深く関与し、助言と提言を積極的に行っている点が挙げられます。取締役会では社外取締役の意見が求められる場面が多く、執行側からの情報提供も十分に行われています。社長との対話の機会も適切に確保されており、意思疎通が円滑に図られています。
また、社外取締役のみで議論を行う「独立社外役員連絡会」も定期的に開催されており、その内容は社長へフィードバックされ、経営課題に対する多角的な視点の共有が図られています。取締役会の実効性評価で明らかになった課題に対しても真摯に対応しており、今後も取締役会やその他の会議体のあり方、意思決定プロセスについて、継続的な見直しを通じ、実効性のさらなる向上が期待されます。
松田 堀井社長の就任以降、2023年には執行役員制度の廃止、2024年には報告セグメントの変更に伴う組織再編など、経営執行体制の再構築が進められています。こうした取り組みは、企業としての変革への強い意志を示すものであり、今後の成長に向けた重要な基盤となると捉えています。
目標として掲げる売上高5,000億円の達成は、組織力を最大限に発揮しなければ実現することが難しい数字です。より実行力のある強固な組織体制の構築に向けて、社外取締役として必要な助言や提言を通じて、今後も積極的に関与していきたいと考えています。
鴨居 企業価値の向上において最も重要なのは、執行側の体制をいかに強固なものにするかという点です。当社は、新たな成長フェーズへ転換しようとしていますが、それに伴い執行側に求められる能力も変化しています。現在は、高い戦略立案能力と実行力を備えたリーダーシップチームへの移行期にあると認識しています。私は、執行側に近い視点を持ちながら後押しすることで、共に新しいステージを築いていきたいと考えています。
金丸 近年、自動車関連業界では不祥事が相次いでおり、企業の信頼性が改めて問われています。当社は、新たな子会社やFC加盟店が加わりグループが拡大していますが、社会から継続的に信頼される企業であり続けるためには、コンプライアンスの徹底と透明性の高い運営が不可欠です。法務の専門的な視点を持つ立場として、グループ全体のガバナンス体制やリスク管理の状況を継続的に確認し、必要に応じて助言・提言を行うことで、健全な企業運営の実現に貢献していきたいと考えています。
小泉 これまでにないスピードでM&Aを実行し、連結子会社が増加している状況においては、グループ全体の内部統制の強化が急務です。常勤監査等委員として、必要な監査や提言を通じて、守りのガバナンスをさらに強化し、持続可能な成長を支える基盤づくりに取り組んでいきたいと考えています。
鴨居 当社はモビリティという社会インフラに関する重要なサービスを提供しており、今後の日本における高齢化の進展を踏まえると、高齢者のためのモビリティやその支援など、社会的役割や当社の存在意義が広く認知されるよう、積極的な情報発信が求められます。
事業の多角化が進む中で、ガバナンスと人材戦略の強化は不可欠です。人材面では、女性管理職比率や育児休業取得率といった定量的な指標に加え、多様な人材が高いエンゲージメントを持って活躍している姿を、外部に向けて積極的に発信してほしいと考えています。
松田 中期経営計画で掲げた施策を着実に実行し、目標を達成することがサステナブルな成長の基盤となります。計画初年度は好調なスタートを切ることができました。今後は組織体制と人材のさらなる強化を通じて変革を加速させ、長期ビジョンである売上高5,000億円の達成に向けて確度を一層高めていくことが必要であり、そのための提案や意見を述べてまいります。

